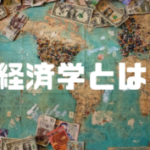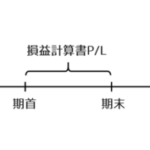古典派とケインズ(ケインジアン)の違いを比較|新古典派(マネタリスト)とは
古典派経済学とケインズ経済学(ケインジアン)との違いを比較
アダム・スミスを祖とする古典派(古典派経済学)とは、ケインズ経済学以前の経済理論の総称です。
ただし、ここではケインズ以後の経済学の学派である新古典派といわれるグループも古典派に含めて考えていきます。
新古典派には、たとえばフリードマンに代表されるマネタリズム(マネタリスト)などがあります。
このケインズ経済学(ケインジアン)と古典派経済学との違いは何なのか両者を比較してみます。
古典派とケインズ経済学の一番の違い
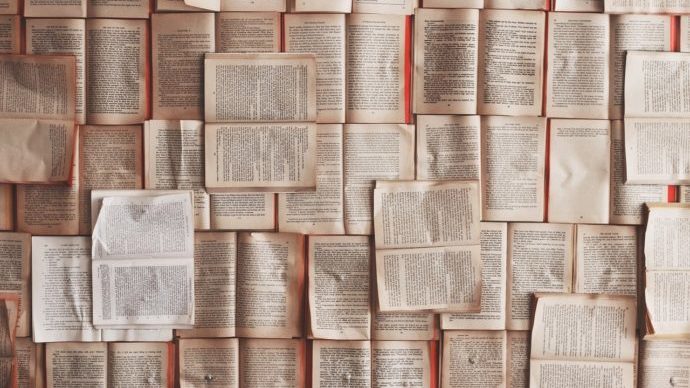
ケインジアンと古典派との一番の違いは市場を信頼しているか否かです。
古典派経済学の最大の特徴は、市場を信頼しているという点にあります。
これに対し、ケインジアン(ケインズ経済学)の特徴は反対で、市場を信頼していないという点になります。
これはケインズの生きた時代に関係しています。
ケインズが生きた時代は、ちょうど世界恐慌があった1930年代で、このときには大量の失業者が発生しました。
これがケインズの市場に対する不信感につながっていると考えることができます。
この市場メカニズムへの信頼の有無、これが古典派経済学とケインズ経済学(ケインジアン)の一番の違いです。
古典派とケインズ(ケインジアン)の比較
では、これを前提に古典派経済学とケインズ経済学(ケインジアン)についてさまざまな観点から比較してみます。
ケインジアンと古典派の基本的な考え方の違い
市場における需要と供給のどちらを重視するか、これがケインジアンと古典派の基本的な違いになります。
古典派の基本的な考え方
まず、古典派は基本的なスタンスとして、供給を重視しています。
これはどういうことかというと、古典派は供給さえちゃんとあれば、後は市場のメカニズムにより最適な状態が実現すると考えているということです。
ケインズの基本的な考え方
これに対して、ケインジアン(ケインズ経済学)は需要を重視しています。これを有効需要の原理といいます。
需要を重視しているというのは、ケインズ経済学は供給だけでは最適な状態は実現できないと考えているということです。
そのために、ケインズ経済学では需要を重視していて需要の量を適切にコントロールすることが重要であるしています。
価格に関する古典派とケインズの考え方の違い
次に、市場で形成される価格についての考え方が、古典派とケインズ(ケインジアン)でどのように違うかをみてみます。
古典派の価格についての考え方
価格について古典派は価格は伸縮的(しんしゅくてき)だと考えています。
伸縮的というのは、自由に動くということです。
そして、古典派は市場の価格調整メカニズムを信頼しているので、政府による介入は不要であると主張します。
市場メカニズムに任せておけば、価格が伸縮的に動く結果、最適な状態が実現できると考えているわけです。
ケインズの価格についての考え方
これに対し、ケインズ経済学では、価格は硬直的で変化しにくいとされます。
ケインズ経済学は市場の価格調整メカニズムは十分機能しないと考えていることから、そのままでは最適な状態は実現せず、 裁量的、積極的な政府の介入が必要だとします。
労働市場についての古典派とケインズの考え方の違い
次に、労働市場について古典派経済学とケインズ経済学でどのような考え方の違いがあるかを確認します。
古典派の労働市場についての考え方
次に、古典派の労働市場についてです。
労働者による労働の供給と企業による労働の需要を分析するのが労働市場ですが、この労働市場における価格にあたるのが賃金(名目賃金)になります。
古典派は普通の市場(財市場)の価格と同様、賃金(名目賃金)は伸縮的に動くと考えます。
労働における価格である賃金が自由に動くということです。
そして、労働の需要と労働の供給に差がある場合には、賃金が伸縮的に動くことによって完全雇用が実現するとします。
完全雇用というのは、非自発的な失業のない理想的な状態のことです。
ケインズ経済学における労働市場の考え方
ケインズ経済学では、労働市場での価格にあたる賃金(名目賃金)は下方硬直的であるとされます。
下方硬直的というのは、賃金が上がるときは上がるけど、逆に下がるときはなかなか下がらないということです。
賃金が下方硬直的な場合、賃金が高い状態のままになるので、働きたいという人のほうが多くなり、(働きたいのに働けないという)非自発的失業が発生することになります。
このようにケインズ経済学では名目賃金が下方硬直的であり、非自発的失業が発生するというのが特徴になります。
古典派とケインズ(ケインジアン)の貨幣理論の比較(違い)
貨幣市場に関する理論である貨幣理論について、古典派とケインズの違いを比較します。
古典派の貨幣理論
古典派の貨幣に関する理論を貨幣数量説といいます。
古典派の貨幣理論では
MV=PY
(M:マネーサプライ、V:貨幣の流通速度、P:物価水準、Y:実質国民所得)
が成り立つとし、マネーサプライMを増やしても、物価水準Pが上昇するだけであり、金融政策は無効だと主張します。
貨幣数量説の式(MV=PY)からもいえることですが、古典派の貨幣理論では、貨幣の需要である貨幣需要は国民所得の関数(増加関数)であり、利子率の関数ではないとされます。
ケインズの貨幣理論
ケインズの貨幣理論を流動性選好説といいます。
ケインズの貨幣理論では、貨幣の需要は取引のための貨幣の需要と資産運用の観点からの貨幣の需要の2種類からなるとされます。
貨幣需要L=取引需要L1+投機的需要L2
これがケインズの流動性選好説における貨幣需要の式になります。
ケインズの流動性選好説では、取引需要は国民所得に正比例する国民所得の増加関数であり、投機的需要は利子率に反比例的に振る舞う利子率の減少関数だとされます。
マネタリズムの特徴

では、次に、別の学説であるマネタリズムについて説明します。
マネタリズムとは、M・フリードマンを中心とするマネタリストによる理論です。
マネタリズムは、古典派の流れを組むマクロ経済学の理論である新古典派の1つになります。
マネタリズムの市場についての考え方
マネタリズムは古典派の流れを組むため、市場を信頼し、政府の介入は不要と考えています。
そのため、マネタリズムでは裁量的な政策を否定して、ルールに基づく政策を提唱しています。
これがマネタリズムの特徴になります。
その具体的な政策がk%ルールです。
k%ルールというのは、貨幣供給の増加率を一定にする政策のことです。
貨幣供給量の増加とは、世の中に存在するお金の量であるマネーサプライMを増加させるということです。
マネーサプライMの増加を一定にすることで、意思決定の遅れなどの裁量的政策の弊害を回避できる、これがk%ルールの意味になります。
タイムラグ
マネタリストがケインズの裁量的な政策を批判する根拠になるのがタイムラグです。
タイムラグというのは、財政政策などを実施する場合に生じるタイムラグのことを意味します。
このタイムラグには、内部ラグと外部ラグという2つの種類があります。
内部ラグが問題を認識し、財政政策・金融政策といった政策を実施するまでのタイムラグであり、外部ラグは政策を実施してから、効果が生じるまでのタイムラグになります。
マネタリストとケインジアンの違い
マネタリストの代表であるフリードマンの自然失業率仮説によれば、裁量的な財政政策は短期的には有効でも長期的には無効とされます。
さきほど述べたタイムラグの存在も裁量的な政策を否定する根拠となります。
これに対し、ケインズ経済学を主張するケインジアンは裁量的な財政政策の有効性を認めています。
この点がマネタリストとケインジアンの大きな違いになります。
古典派経済学とケインズ経済学の比較は以上です。


 https://biztouben.com/time-lag-built-in-stabilizer/
https://biztouben.com/time-lag-built-in-stabilizer/